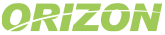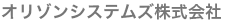サッカー指導者、西野朗氏特別講演
毎年6月に新年度を迎える弊社では、全社員に向けて1年の振り返りと次年度の方針を共有し、親睦を深める全社集会を執り行っております。 今回は弊社代表、菅が同じ高校出身というご縁もあり、プロサッカー指導者である西野朗様にお越しいただき、「サッカーにおけるチームマネジメントと組織論」 というテーマでお話しいただきました。
西野朗氏 特別講演「サッカーにおけるチームマネジメントと組織論」

プロサッカー指導者
西野 朗 (にしの あきら)
1955年生まれ。埼玉県立浦和西高校を経て、早稲田大学在学中に日本代表入り。
その後日立製作所へ入社し、1990年まで現役サッカー選手として活躍。
引退後はサッカー指導者として国内のクラブチームを幾度となく優勝へ導き、
アトランタオリンピック、及びワールドカップロシア大会において
サッカー日本代表監督を務めるなど多岐にわたり活躍。
国内リーグでの監督通算270勝は歴代1位となり、未だ破られていない。
個々の能力の発掘と最大化

会社組織においては性別や年齢はもちろんのこと、性格やバックグラウンドの異なる人々がチームとなって業務にあたることが多く、個々人の強みや特性をどのように組織に活かすか、というテーマがしばしば課題となります。
西野氏は監督として預かった選手達は皆自分自身の財産であり、一人ひとりの才能や能力を見つけ出し、それを最大限に引き出すことが重要だと語ります。 選手によってスキルレベルは様々でも、シーズンを通して色々な角度からその選手を見ると、 「ここを伸ばしていけばチームの戦力になる」「スタートポイントではなく、ここぞというワンポイントで起用しよう」など、 その人の強みを最大限に生かした、適材適所の人材配置が見えてくると言います。
「選手の意見を色々と引き出した中でチームは動いていくものだと思っている。コミュニケーションを怠らないことが大切。選手の小さな変化にも気づけるように目を配っていた。」 と語る西野氏は、各選手の能力を最大限に引き出すためにトレーニングや試合でのフィードバックを積極的に行なっていたそうです。
このような西野氏の考え方は、会社の事業運営においても必要な視点だと言えるでしょう。 多様な人材が集まる企業では、従業員それぞれの強みやスキルを見つけ、それを活かして最適な役割を与えることが組織全体の成功に繋がります。 従業員一人ひとりの特性を捉えるためにはまず、管理者層と従業員との対話が重要になってきます。 日常的なコミュニケーションを通じて、相互に関わり合うことで信頼関係を築くことが不可欠であり、従業員の意見やフィードバックを積極的に取り入れることで、個々の能力を発見し、それを最大限に引き出すことが可能となります。
しかしながら、必ずしも全員が意見を述べてくれるとは限りません。 西野氏は、「主力選手ほど自分の意見を持っていることが多く、こちらから求めずともどんどん発言してくれる傾向が強い。そのため、サポートメンバーにこそどう思っているのか発信させるように、意図的に指名して意見を聞くようにしていた。」と語ります。 相手からの意見を待つだけでなく、こちらから働きかけることが結果として従業員の潜在能力を引き出すことに繋がり、組織全体のパフォーマンス向上に繋がると言えるでしょう。
個の成長をチームの成長へ波及させる

スポーツチームにおいてはチームワークが鍵となる以上、個々人の成長はもちろんのこと、その成長がチーム全体の成長へ波及してゆくことが極めて重要になります。 これはスポーツに限った話ではなく、事業部や部門・グループ単位で業務を進める会社組織においても同様のことが言えるでしょう。 個の成長ひいてはチームの成長を実現するためには、以下2つの要素が鍵となります。
まず第一に、自分自身がチームに対してどうしてほしいのか、己の意見をしっかりと伝えることが重要です。 意見を明確にすることでチーム全体の方向性が一致しやすくなり、個々の成長を促すとともに、それがチームの成長へと自然に波及していくからです。
「意見交換は大歓迎でした。」西野氏は自由闊達な議論が時に化学反応を引き起こし、新たな戦略や戦術の発見に繋がった、と過去を振り返ります。 行き過ぎた迎合は結局何も生み出さずに終わってしまうため、周囲への主張はエゴではなく、むしろチーム全体のパフォーマンスを向上させるための重要な要素になると言います。 「自分のプレーを最大限に引き出したい」という思いがあるからこそ、どのように周りを活かすかを考え、要求していく―それが自分のパフォーマンスを最大限に引き出し、チームを活性化することに繋がるそうです。
そして第二に、自己理解を深めることが重要です。自分の強みと弱みを把握することで、適切なタイミングでチームに貢献することができます。 西野氏は「一流選手ほど自分自身を深く理解しており、自分の力には限界があることを認識したうえで、周りがどうすればその力を最大限に発揮できるのか知っている。」と語ります。 このような自己理解によって、周りに対して具体的な支援を求めることができ、結果として自分だけでなくチーム全体に還元することができるのです。
強固なチームを築くには

西野氏はこれまで、サッカー監督としてクラブチームを何度も優勝へ導いてきましたが、ポイントとなったのはいわゆる「チームワーク」や「グループワーク」だったと言います。 チーム全体が結束し、相互に影響し合いながら戦う姿勢こそが理想的であり、チームに貢献しようと異なるポジションにもチャレンジする、ポリバレント性のある選手は特に貴重だと語ります。 こうした選手がいることでチーム全体の柔軟性が増し、様々な状況に対応できるようになるからです。
「監督の意思というものは色々な形で伝え続けることが大切。何を考えているのか、何がしたいのか、と選手に思われてしまってはいけない。」
選手たちが監督の考えや目標を理解し共有することで、チーム全体が一丸となって動くことができると西野氏は主張します。 これは企業で働く人々にとっても同様で、上司や管理者は会社のビジョンを提示し、そのビジョンを実現するためにどのような形で行動すべきかを従業員に伝える必要があります。 会社の考えが明確であればあるほど、従業員は安心してその指示に従い、全力で業務にあたることができます。
また、西野氏は「チームワークは監督と選手間だけのものではない」と強調します。 メディカルチームやサポートチームとも同じ目標を共有し、一体となって取り組むことが強固なチームづくりに必要不可欠です。 会社の事業運営においても、営業や事務・エンジニアなど職種や役職の異なる人々が共通の目標に向かって協働することで、 会社全体のパフォーマンスを向上させ、結束力のある強固なチームに繋がってゆくのです。
全社集会を終えて
講演の終盤、西野氏は以下のように語りました。
「組織は生ものです。時には自分の思い通りにいかないこともあるでしょう。そのためには、こだわりを持って貫き通す部分と、変化に柔軟に対応する部分のバランスが重要です。リスクを負ってでも果敢に挑戦する姿勢が求められる場面もあります。」
今回「サッカーにおけるチームマネジメントと組織論」というテーマでお話しいただいた西野氏の講演には、会社組織にも共通する多くの教訓が散りばめられていました。 個々の努力とチーム全体の結束力、明確な意思表示の重要性、全員でのビジョン共有と連携など、 ビジネスの成功にも直結する要素が多く、我々社員にとっても学ぶべき点が非常に多かったと思います。
新年度を迎えるタイミングで実現した本講演ですが、年度末までフレッシュな気持ちを忘れることなく、 全社員が一丸となって仕事に取り組んでいく気概が感じられる全社集会となりました。